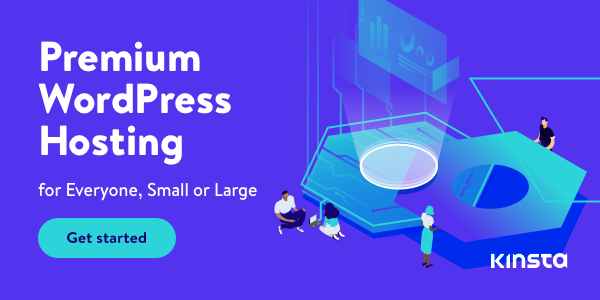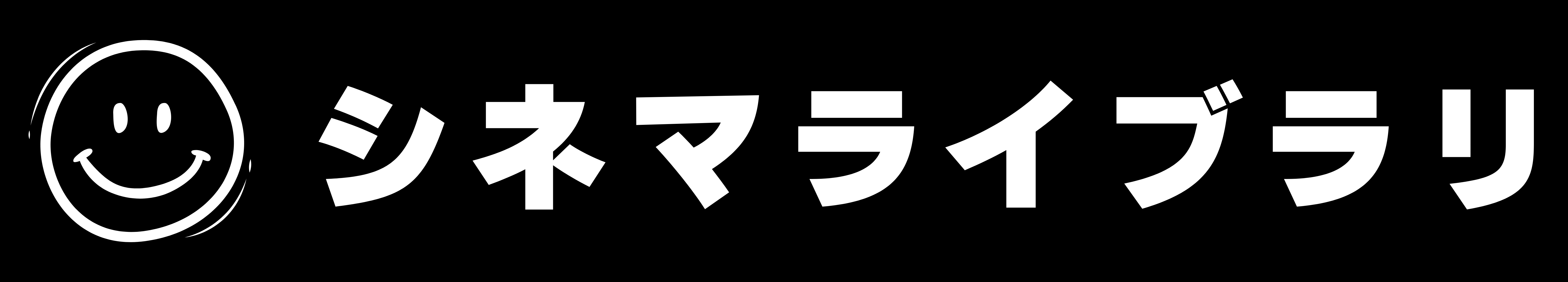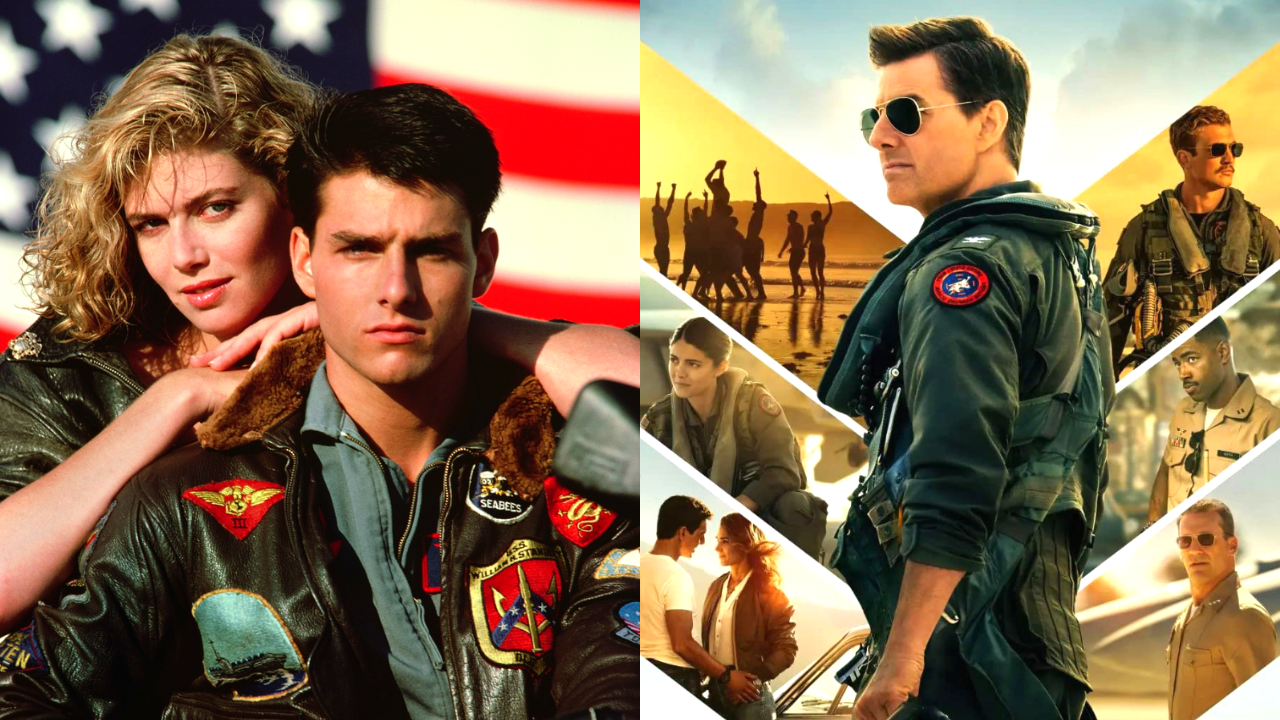劇団おぼんろ「 瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった 」考察レビュー

映画ライフ楽しんでますか? 今回は、ペンネーム@あるなんさんからの投稿レビューです。
劇団おぼんろによる、59歳の生きることに絶望している男性が、7日間の夢から生きる希望を、未来のための想像力を取り戻す物語。
演技で観客を物語の中に連れて行ってくれる役者たちは見事であり、普遍的な物語に老若男女が感動するエンターテインメント作品となっております。
画像の引用元:公式サイトより
(アイキャッチ画像含む)
瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった

公開日
2021年11月12日
上映時間
152分
キャスト
- 末原拓馬(脚本・演出)
- さひがしジュンペイ
- 塩崎こうせい
- 末原拓馬
- 高橋倫平
- わかばやしめぐみ
予告編
公式サイト
作品評価
[rate title=”5つ星”]
[value 4]映像[/value]
[value 3]脚本[/value]
[value 3]キャスト[/value]
[value 2]音楽(BGM)[/value]
[value 4]リピート度[/value]
[value 1]グロ度[/value]
[value 3.5 end]総合評価[/value]
[/rate]
感想レビュー
映画とは違い、背景も変わらなければ役者も5名のお芝居です。
所狭しと動き回り、あるときは海のように、またあるときは裁判所のように。
演者のパフォーマンスから、その世界が広がっていくのを感じます。
芝居は映画と違って、観客の想像力を試してくるエンターテインメントだと改めて感じました。
そんな中でも、劇団おぼんろの面々は演技が素晴らしく、過多に感情移入してしまうほど物語に没頭してしまいました。
この物語、テーマは「 生きよう、現在のために未来を想像しよう!」という普遍的なものでした。
よくあるメッセージだと思うのですが、それを紡ぐストーリーや芝居が素晴らしく、前向きに生きるためのパワーを貰えました。
芝居冒頭に、ナレーションで「 この物語は夢オチです。
主人公が最後に「 なんだ夢か、いい夢だったな 」と言ったら幕が閉じます。
と、ネタバレ的なことを言うのですが、幕が降りた後に、「 いい夢だったな 」と、まるで自分が見ていた夢から覚めた気分で口走っている自分がいました。
ごく普通の59歳の男性が睡眠薬で自殺を図るところから始まります。
クラゲが現れて瓶から海を作り裁判所まで連れて行かれ、「 小学校3年生の夏休みの宿題を提出してない罪 」で7日以内に宿題と自由課題を終わらせることとなりました。
宿題はいいのですが、自由研究がなんだか分かりません。
自由課題はなんだったのか夢から夢へ旅をすることになるという、ちょっと摩訶不思議な夢の旅なのかな?
と感じましたが、中盤から終わりにかけて、色々な真実やそれぞれのキャラクターの思いが錯綜してハラハラドキドキの展開が待っております。
最後には、みんなの想像が膨れ上がり、信じることを諦めかけていたクラゲも未来のために想像の翼を広げ、クライマックスへなだれ込むのでした。
普遍的な物語なので、途中で真実は想像できちゃうんだけど、それでも芝居が一級品なのでドキドキせずにはいられず、最後まで楽しめました。
まとめ
主宰の末原拓馬さんがカーテンコールの時に言っていましたが、「 僕たちの大切な物語です 」
「 物語なので、物語られることで生きながらえる 」
「 みなさまも、どうかいろいろなところで物語ってください 」
と素敵なコメントをされていました。
物語をその様に捉えたことがなかったため、主宰の言葉のセンスや感受性も含めて、改めてこの作品が好きになりました。
まずは、妻や娘に物語ってみたいと思います。