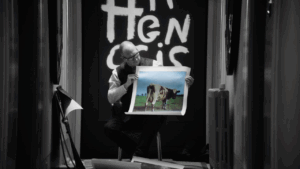災害大国、日本。特に地方での災害は頻繁に起こる。
するとそのときは皆、「 できることはないだろうか 」と考え、行動に移す。
しかし、残念なことに災害だけではない事件が次々と報道されるため、人々はいつの間にか、被災地の人たちを忘れてしまう。
被災地を定期的に訪れ、大変な状況で前向きに生きる人たちを撮影した短編ドキュメンタリー「 NOTO, NOT ALONE 」は、被災地の人が本当に求めているものは何かを知るヒント。
まだ雪の残る3月、映像作家の小川紗良さんが炊き出しの風景を追った2日間の濃密な「 人間と時間 」が、あれから一年を迎える今、私たちに問いかけるものは何だろう。
NOTO, NOT ALONE

上映時間
35分
予告編
キャスト
- 小川紗良(映像作家)
- 三上奈緒
ほか
公式サイト
制作:合同会社とおまわり
むしろ、以前よりも健康的なものを食べさせてもらっている

教師の一人が作品の中で言った言葉だ。この言葉の通り、炊き出しの現場では、健康面や安全性を考慮した献立が決められていた。
この献立を作っていたのは、作品で大きな役割を果たす三上奈緒さん(旅する料理人)。
彼女は調理室と思われる場所で、テキパキと動きながら皆に指示を出す。
ホワイトボードに書かれているのは、各種食材と量、その他の細かい指示。
生徒がアツアツの給食を食べられるように逆算して、調理段階をタイムスケジュールで可視化している。
この日のメニューは「 イノシシ麻婆豆腐 」、三上さんのはつらつとした声が飛ぶ。
ホワイトボードを見ながら「 ここまではとにかく刻む、そしてここから火入れね。あと男子はよく食べるからもう一つ炊飯器ないかな 」
三上さんは自分の理念を語る。
「 食(しょく)って、体も作るけど心も作るから。それと被災地だからといって簡単なものにこだわることはない。いつも通りのもの。調味料もオーガニックの高価なものを買ったり、野菜も生産者の顔が分かるもの 」
こういうときだからこそ、いつも通りのものを食べて活力にする。我慢しなくていい、という優しさが伝わってくる。
実際に調理しているときよりもうんと穏やかな口調で話す人だ。
「 こんなときに、炊き出しにそこまでやることない 」という考えの人にも、彼女は自分のやり方を貫く。
そこにブレがない。こういう姿勢も十分、高校生や周囲の人々に元気を与えていた。
こういう状況で駆けつけてくれる人は前向きな人
きっと、悲惨な状況にやってくる人は本質的に前向きなのだろう。
中には子連れの人もいた。
「 子どもがいたら迷惑と思っていたけど、来てみたら、大丈夫だった 」
母親たちが給食作りをしている横で喧嘩する子どもたち。
彼らにとって、今、なぜ自分が能登にいて、能登で何が起こっているのかを理解するのは無理だ。
私はこの子どもたちの様子を見て、大人はもっと言葉では表せないストレスを抱え、誰かと一触即発で喧嘩してもおかしくない状態なのだろうと感じた。
ましてや、多感な思春期である高校生の避難所暮らしというのは、大人とはまた違うストレスを抱える。
しかし「 大変だけど、トイレに一人で行けないおばあちゃんを手伝ったりもする 」と答えた女子高生は暗い表情ではなかった。
こういう状況だからこそ、誰かに何かをしてもらうというより、誰かの役に立つことで自分の存在意義を見出す人がいるのだと思った。
高校生でそれを知った彼女の未来を、私は「 大丈夫だ、この子は! 」と思った。
一方で、前向きな人たちばかりが登場するわけではない。
未だに震災の痕跡をまざまざと見せつけられるシーンも登場する。
町に一件しかなかったスーパーの看板が見事に傾いていた。
どうやって何を食べているのだろう。食材は、物資が届いたとしても水がないのだから、作れるものは限られている。
(能登の人は大丈夫なんだろうか)という思いを視聴者に残して、場面は再び炊き出しのシーンに戻る。
生徒たちが食器を持って給食の列に並ぶ。
水がないので使った食器を洗えない。そのため、食器にラップを掛けて、その上におかずを乗せる。
ラップをすればゴミが増える。だが、水不足を考えると洗うことも難しい。
三上さんはある生徒に問いかける。ラップをかけずに食べてもいい。汚れは拭き取ればいい。
どちらにしてもゴミは出るのだが、食器をキッチンぺーパーに似た紙で拭き取りながら女子生徒が言った言葉が印象的だ。
「 同じご飯なのに、ラップをかけずに食べた方がおいしかった気がする 」
ここでラップを使用するかどうかの判断はとても難しいと思う。
この女子生徒たちに触発されて、皆が食器に直接、給食を入れたかというとそうではなかった。
炊き出しの場面では、このような個人の考えや行動も描かれている。
色々な意味で選択の余地がない避難所暮らしの中、情報にしても食べ物にしても、何が自分にとって必要なのかを取捨選択する力が養われたのではないだろうか。
このような状況にならなければ考えることができないほど、日常を幸せに過ごしている私は自分をぬるいと感じた。
しかし、体験してみないと分からないことの方が多いのだ。
だからドキュメンタリーを通して想像し、疑似体験することが大切だし、伝えたい。
今の能登は面白い、おいで!
映画は炊き出しの様子がメインなのだが、食材提供という大切な要素として登場するのが、オーガニックとフェアトレードの店「 のっぽくん 」だ。
取締役の女性は、調理の現場へ食材を届ける立場として登場するのだが、彼女でさえ、最初の10日間は何もできない状態であったという。
たくさんナプキンが届くけど、それより必要なのは、お風呂に入れないから(下着が汚れるのを防ぐために)ライナーの方が大事であるなど、現地ならではの「 必要なもの 」が明確になっていったそうだ。
自分にできることは何だろうと考えたときに炊き出しする人への食材支援。
今までのネットワークを生かし、知り合いの農家さんなどから、安いものを多く仕入れて回していくことだったと。
遠くにいる私たちが考える「 何ができるだろう 」と、近くにいる人の「 何ができるだろう 」の観点が違うのは当然なのだが、切実さが違う。
彼女は声を詰まらせて自分ではない周囲の人の困難を訴える。
おじいちゃんやおばあちゃんが、家から大切なものを取り出せない状況、子どもたちの食環境が悪いことなどを挙げ、そういったことは全てボランティアに丸投げされると嘆く。
国の補助金はなく、全て寄付やボランティアで賄っている。
他の被災地であれば一ヶ月で復興できることが能登ではできていない。
それでも彼女は舞台となる高校に食材を届けると、ボランティアに来ている人たちの明るさ、おもしろさに嬉しくなるようだ。
表情が途端に明るくなる。
そして「 その集まった素敵な人たちと高校生との化学反応がすごい。他にはないものが能登にはある。今の能登は本当におもしろい、能登においで 」と。
私たちができるのは、「 何ができるかを考えるのではなく、能登の人が望んでいることを実行に移すこと 」
これが私がこの映画で見つけた答えだ。
「 NOTO, NOT ALONE 」能登は一人じゃない。そして今こそおもしろさが分かる場所だ。
 執筆者
執筆者文・インタビュー:栗秋美穂
↓映像作家・小川紗良さんインタビュー記事はこちら
「 能登の魅力を届けたい 」小川紗良が語る映画制作と能登への思い【 インタビュー 】
↓その他のおすすめドキュメンタリー映画記事はこちら
【 ネタバレあり 】ドキュメンタリー映画「 大きな家 」感想レビュー、「 どんな環境でも自己ベストは出せる 」