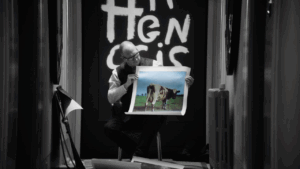映画監督であるデイモン・ガモーは、愛娘・ベルの未来に対する不安をきっかけに、このドキュメンタリーを制作したそうです。
オーストラリアでのNo.1ヒットドキュメンタリー作品である本作。
問題を提起するのではなく、解決策を見出すことを目的に作られ、多くの事例の中で農業と海洋生物の多様性について考察します。
視聴後、あなたは、解決策を見出すことができるでしょうか。
2040 地球再生のビジョン

あらすじ
4歳の娘を持つオーストラリアの映画監督デイモン・ガモーは、娘たちの世代には希望を持てる未来に生きてほしいと願っている。悪化する地球環境を懸念する中で、もし地球環境を再生できるようなアイデアや解決策が今後急速に世界中に広がったら、娘が大人になる2040年にはどんな未来が訪れるだろう?と、現実的な解決策の実行者や専門家に会うため欧州各国やアジア、アフリカ、米国と世界11ヶ国を巡る旅に出る。その中で取り組むべき問題の数と同じくらい、すでに実践可能な解決策が沢山あることを知る。また、各地で約100人の子どもたちに理想の未来についてインタビューし、彼らの“希望”に刺激を受ける。(公式サイトより引用)
原題
2040
公開日
2025年1月11日
上映時間
92分
予告編
キャスト
- デイモン・ガモー(監督、出演ともに)
- エバ・ラザロ
- ゾーイ・ガモー
- ジェネビーブ・ベル
- フレーザー・ポーグ
- アマンダ・カーヒル
- リアン・ポーグ
- ポール・ホーケン
- ケイト・ラワース
- ブライアン・フォン・ハーゼン
- トニー・セバ
- ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ
- コリン・セイス
- シャロン・ピアソン
- ニール・タムハネ
- ジョン・E・ピーターソン
- エリック・テーンスマイヤー
公式サイト
食料生産と農業の変革

リジェネラティブ、 再生農業と呼ばれるものが注目されています。
土壌の健康を改善し、炭素を土壌に貯める農法です。
土壌に貯められた炭素が大気中に漏れると二酸化炭素の排出になるので、最近では、土の上にカバークロップなどの工夫もされています。
この農法は、気候変動を緩和するだけでなく、食料の質と安全性を向上させる効果もあります。
土を耕す従来型のやり方と違い、不耕起栽培の方が栄養価が高いことも分かっているのです。
再生農業の先駆者であるコール氏は「 従来の農業では、土壌は衰弱していく一方だった。しかし、再生農業に転換してからは、土壌の力が蘇り、作物が力強く育つようになった 」と語っています。
日本でも少しずつ取り入れられている農法です。
「 マルチスピーシーズグレージング 」の登場
オーストラリアの農家が実践する「 マルチスピーシーズグレージング 」という方法が出てきます。
これは、同じ場所に数種類の植物を栽培し、牛や羊などの家畜を短期間で移動させながら食べさせる方法です。
この方法により、土壌への負荷を分散させ、土壌の健康を維持しながら家畜の生育にもよい影響を与えます。
なぜかというと、牛たちが一ヶ所の土壌を踏み固めることを防ぎ、その糞尿が自然肥料として土壌を豊かにするからです。
畜産のように、家畜を狭い場所に閉じ込めて飼育するのではなく、自然に近い環境で放牧することで、土壌への負担を軽減しているというわけです。
自然なやり方に戻りつつあるのです。
水が大切
再生農業は、土壌の保水力を高めることで水資源の保全に貢献します。
健康な土壌はスポンジのように水を吸収し、保持することができます。
再生農業によって土壌の有機物が増加すると、土壌の保水力が向上し、干ばつや洪水などの被害を軽減することができます。
それでは、どうすれば保水力を高められるのでしょうか。
それは、化学肥料や農薬の使用をやめることです。
これらは土壌の微生物の活動を制します。
つまり、肥料や農薬の使用を軽減することで土壌本来の力を活かし、健全な土壌を育むことができるため、保水力が高まるのです。
このように、保水力を高めるには化学肥料や農薬の使用を減らせばよいので、持続可能な取り組みです。
再生農業と畜産
世界的な食肉消費量の増加は、環境負荷の増大に繋がっています。
映画では、「 私たちが食べる肉は、理想的には再生農業によって生産されたものであるべきだ 」という専門家の意見が紹介されています。
しかし、 従来の畜産では家畜を狭い場所に閉じ込めて飼育し、穀物などの飼料を与えることが一般的です。
ほとんどが繁殖させたものです。
狭い場所に閉じ込められて人工的に飼育された動物たちを見て、私は動物虐待という言葉を思い出しました。
それなのに、その家畜たちのお肉をおいしいと食べている自分の矛盾。
作品は決して私を責めてはいません。
事実をありのままに映し出すことで、解決策を見つけようとする人、仕方ないと諦める人に二分される映画だと感じました。
海洋パーマカルチャー
ブライアン博士は「 地球温暖化の影響で海水温が上昇し、海の循環が滞っている。栄養不足で海洋生物が減少している 」と危機感を露わにします。
海洋パーマカルチャーは、この問題を解決するために、海藻(昆布など)を栽培するプラットフォームを海に設置し、深海から冷たい栄養豊富な水を汲み上げることで、海藻の成長を促進し、海洋生態系を回復させます。
海藻は二酸化炭素を吸収し、海の酸性化を防ぐだけでなく、食料や肥料としても利用することができます。
その上、大気中の二酸化炭素濃度を削減することで、気候変動の緩和にも貢献しているのです。
また、海藻は栄養価が非常に高く、乾燥させれば料理の出汁にもなり、持続可能な食料源となりえます。
ブライアン博士は「 海洋パーマカルチャーだけで100億人を養える 」と断言しています。
海藻プラットフォームとは?
さて、このパーマカルチャーにとって必要な「 海藻プラットフォーム 」とはなんでしょう。
リサイクル素材で作られたプラットフォームに海藻を植え付け、海面に浮かべることです。
このあたりは映像を見た方が分かりやすいです。
波の力で動くポンプを使って、深海から栄養豊富な冷たい水を汲み上げ、プラットフォーム上の海藻に供給します。
私も知らなかったのですが、海藻は水面を通した光で光合成を行うのですね。海水中の二酸化炭素を吸収するのです。
また、海藻は魚や貝類などの海洋生物の住処や産卵場所となり、生態系全体の回復に貢献します。
いいこと尽くしなのです。
新しい雇用の創出
漁師にとって、冬は稼ぎ時ではありません。
しかし海藻の栽培、加工、流通など、海洋パーマカルチャーに関わることは通年で行われ、新しい雇用、事業へと繋がります。
「 海洋パーマカルチャーが食糧危機や環境問題の解決に役立つ未来を想像してみてください 」と、まるでパーマカルチャーには「 希望 」しかないように、デイモンは語ります。
海藻は食用として、また動物飼料、肥料、繊維、バイオ燃料など、さまざまな用途に利用できるので、デイモンがそう言うのも無理はないかもしれませんね。
今回は、リジェネラティブ、再生農法の紹介で、持続可能な取り組みを知り、海洋パーマカルチャーでは生物多様性を守ることの大切さを学びました。
子どもたちの言葉が伝えるもの
最後に、映画の中に登場する子どもたちのインタビューで印象的だったシーンをご紹介します。
まず最初に登場した彼らは、気候変動問題に対する率直な意見や、未来への希望を語っていました。
彼らの言葉には、私たち大人に、未来を担う子どもたちのために、今すぐ行動を起こさなければならないという強いメッセージを感じました。
子どもだからこそ、真摯に訴えかけてくるものがありました。
次に、最初に描かれたソーラーシステムの問題について。
バングラデシュの子どもたちは、ソーラーホームシステムの普及によるエネルギー事情の改善を歓迎しています。
子どもは「 皆が自分の力でエネルギーを作れるようになるなんて素晴らしい 」と目を輝かせていました。
そして3つ目。
オーストラリアの子どもたちは、地球温暖化や汚染問題について、政府の対策の遅れを指摘し、積極的に行動を起こす必要性を訴えていました。
しっかりしていて驚きました。
「 世界中のゴミを全部吸い上げて、別の次元に捨ててしまいたい 」といういかにも子どもらしい発想は、不可能ですが、そうしたい気持ちは十分理解できました。
作中のインタビューから、子どもたちは大人よりも環境問題に対して高い関心と、よりよい未来への希望を持っていることが分かり、私は未来に希望が持てました。
気候変動問題は深刻ですが、解決策は既に存在し、世界中で多くの人々が行動を起こしています。
私たち一人ひとりが未来のためにできることを考え行動することで、よりよい未来を創造することができるのです。
 執筆者
執筆者文・ライター:栗秋美穂