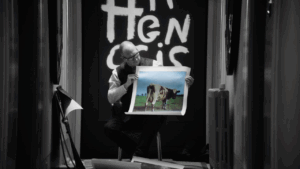本ドキュメンタリーは2012年、NPO法人ACE設立15周年記念映画として制作された。
本作品のテーマである「 児童労働 」について考える一方、筆者がもう一つの視点から、2012年に作られたこの作品を現在の2025年に当てはめて考察します。
甘い、すっぱい?ん~美味しいかな
これが誰の言葉か、分かりますか?
アフリカはガーナ、カカオ農園で働いているお母さんの言葉です。
お母さんは何を食べて、「 ん~、美味しいかな 」と言ったのでしょう。
チョコレートを食べて言ったのです。
おかしいと思いませんか?チョコレートの原料であるカカオを作っている当事者はチョコレートを食べたことがなかったのです。
ガーナの人にとってチョコレートは高級品のため、原料を作っている彼らはそれがチョコレートとなった姿さえ見たことがないのでした。
ガーナでは、子どもも立派な働き手

児童労働、それは文字通り、児童が労働することです。義務教育である学校に行かず、カカオ農園で働きます。
それは「 家のお手伝い 」というレベルではありません。そんな貧しい農村に、日本から3人の女子高生がやってきました。
彼女たちは、実際のカカオ農園で一日、作業をします。現地の人と共にカカオを収穫し、そのカカオを割るのも一苦労。
ある男の子は9歳から、約20㎏あるこのカカオを、頭上に乗せ歩いて1~1時間半、歩いて3往復していたのです。
最初は好奇心でいっぱいでやってきた彼女たちですが、現地の苛酷な作業を体験し、疲労と暑さが加わり、ダウンして横になります。
ガーナの子どもたちは皆、夢を持っている

実際にカカオ農園の仕事を体験した彼女たちが次に訪れたのは現地の学校。将来、何になりたいかと生徒たちに尋ねると、全員が考える間もなく答えます。
「 医者になりたい 」「 看護師になりたい 」「 教師になりたい 」皆が明確な目標を持っていました。
しかし、こうして学校に通い、夢を持っている彼らはここでは恵まれています。学校に行けない子も多いのです。
前述したように、働かなればならないからです。彼らは、夢さえ抱く余裕がないでしょう。もしかしたら、カカオ農園以外の仕事があることすら知らないかもしれません。
映画ではまず、親の意識改革が大切であると説きます。親が、教育の大切さを理解することです。
「 貧しさから抜け出すためには教育が必要 」と気付くことが第一歩なのです。
私はここでふと、メモしている手が止まりました。
日本では、何のために教育が行われているのか。
日本の子どもはホワイトカラーが夢なのか
私には小学校5年生、早生まれで先日11歳になったばかりの息子がいます。学校では、息子の歌が歌われているそうです。
♪中卒、中卒~、ホワイトカラーは無理っ、無理っ~、という歌です。息子はガーナの子ども同様、明確な夢があるので、歌われても気にしていませんが、「 ホワイトカラーってなに?」と聞かれた時、私は思いました。
ホワイトカラー企業に就職するために、放課後、お弁当を持って遅くまで塾に行き、中学受験の準備をしているのは、そのためだったのかと。(もちろん違う理由のお子さんもいると思います)
我が子も私立の一貫校に通っていましたから、中学受験を否定していません。しかし「 ホワイトカラーが夢 」だったことには、言葉を失いました。
こうして私立、あるいは国公立中学を目指す子どもたちがいる一方で、日本では不登校という現実があります。この映画が公開された2012年の不登校児は約11万人でした。
現在2025年は過去最多の35万人です。こう考えると戦慄さえ覚えます。
学校に行きたいガーナの子、学校に行けない(行きたくない)日本の子

夢を持って生きてほしいと願う親は多いです。
夢を見つけるために、やりたいことを見つけるために、最近では様々な体験プログラムがあります。ガーナの先生は、なぜか涙が溢れてくる彼女たちに言います。
ここは毎日問題が溢れている、それが当たり前であると。だから生徒たちはそれを解決するために「 なりたい職業がある 」
そのように私には聞こえました。この町には医者が少ないから医者になりたいという女生徒の言葉がまさにそれです。
問題を見つけ、それを自分で解決するために将来の夢がある、ここが日本とガーナの子どもの大きな違いではないでしょうか。
児童労働や貧困など、目の前にある社会的問題を日常的に見ているガーナの子ども。社会的問題とは別の問題があり、学校に行きたくない、行けない日本の子ども。
ホワイトカラーを夢に、ストレスを感じながら奇妙な歌を歌う子ども。みんな、同じ子どもなのに、何が違うのでしょうか。
これもまた、児童労働しかり、一朝一夕では解決しない大きく深い闇です。さて、話は戻ります。
ガーナを訪れた女子高生3人が日本に帰国してから、どのような反乱、一揆を起こしたのかはぜひ、本編をご覧ください。今の18歳の女子高生に、彼女たちと同じくらいの熱量があることを願います。
 執筆者
執筆者文・ライター:栗秋美穂