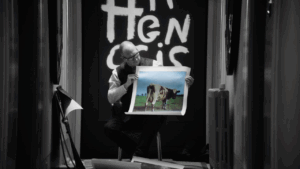あなたはどんなときに「 もったいない 」と思いますか?
チャンスを逃した瞬間?それともお金を無駄遣いしてしまったときでしょうか。
食品に関しても「 もったいない 」という言葉を使いますよね。
今回ご紹介する映画「 もったいないキッチン 」は、食品廃棄に焦点を当てた映画です。
一見難しく思えますが、私たちがすぐにでも実行できることはあるはずです。
もったいないキッチン

あらすじ
“もったいない精神”に魅せられ、オーストリアからやって来た食材救出人で映画監督のダーヴィド。日本を旅して発見する、サステナブルな未来のヒントとは。
(公式サイトより引用)
公開日
2020年8月8日
上映時間
95分
予告編
キャスト
- ダーヴィド・グロス(監督・出演ともに)
- 塚本ニキ
公式サイト
はじめに

2024年現在の日本では、一人が1日に廃棄する食品は100g。おにぎり1個分に相当します。
これを年間に換算すると、日本全体で約480万tの食品が捨てられていることになります。
もったいないだけではありません。
「 捨てる 」という行動にはお金が必要で、不要なガスを排出することにもなります。
プロパンガス会社検索 「まちがす-MACHIGAS」
この映画の監督兼主人公、そしてナビゲーターの役目を果たすのはオーストラリアからやってきたダーヴィド。
彼は、前作「 0円キッチン 」(2015)で欧州を舞台に、廃棄される食材を次々とおいしい料理に変身させた食材救出人です。
そんな彼が今回舞台に選んだのは、「 mottainai精神 」の国民性がある我が国・日本。
彼は通訳を兼ねたパートナーのニキとともに、4週間で1,600km、日本全国をキッチンカーで旅しながら、
「 どうすればもったいないをなくせるか 」のヒントを探ります。
今回、私がご紹介する人々はどなたも、あるものを工夫して食べることでフードロスに貢献している、という共通点を持つ人々です。
捨てるはずのものだって食べられる
まず最初にご紹介するのは、精進料理。
精進料理の特徴は、野菜・豆類など、植物性の食材を調理して食べることです。
ダーヴィドたちは浅草のお寺を訪ねて、この精進料理で不思議な体験をします。
住職からアイマスクを渡され、見えない状態で食べる「 暗闇ごはん 」です。
はじめこそ、日本の寺という和文化に触れワクワクを隠せないダーヴィドですが、
住職からアイマスクを渡されると、途端にカメラを向いて不安そう。
それを無理して笑っているのが面白かったです。
一方、ニキは恐れず果敢にアイマスクを装着。いつの時代も女性の方が逞しいですね。
さぁ、ここからはこの映画で唯一、緊張するシーンです。
消費期限が切れた食品でも臆さずに食べてしまうダーヴィドもこれには大苦戦しました。
なにせ見えないものを食べる。得体の知れないものを食べることほど、恐ろしいことはありません。
パートナーのニキは、あまりにも上手に食べられない自分を笑っています。
しかしダーヴィドは違います。最初こそ笑っていましたが、すぐに集中モードです。黙って真剣にお箸で食べ物を探ります。
精進料理は、正方形のお盆に小鉢がいくつも並んだものです。
最初の難関はお盆を見つけて、次にお皿、それを落とさないように口元へ持っていきます。
それだけでも大変なのに、今度はお箸が小鉢に入らず空振りばかり。
やっと掴んで食べたときのダーヴィド、アイマスクしていても満足な笑顔が伝わってきました。
さて、アイマスクを外した彼らの前に、手付かずの精進料理が出てきました。
自分たちが食べていたものはこれだったのか、とニキも不思議そうに覗き込みます。
ダーヴィドはその中の小鉢の一つ、濃いこげ茶色の塊を見て尋ねます。
「 これはなんですか 」
住職は、「 茄子のヘタを煮たものです 」と答えました。
これにはニキが驚きました。
「 ヘタって普通、捨てますよね 」
ダーヴィドも納得したように頷きます。
実はこの茄子のヘタを煮たものは、ダーヴィドが今回の料理で一番おいしいと思ったものでした。
しかし、もしこの黒ずんだ姿を見ていたら、ダーヴィドは手を付けなかったかもしれません。
いつの間にか我々人間はビジュアルでおいしさを判断しているのですね。
見えない分、感覚を頼りにゆっくり味わったからこそ気付いたおいしさでした。
茄子のヘタは捨てるものと、多くの人はそう思うかもしれません。
しかし、自分の常識が常に正しいとは限りません。
認識を変え、新たな行動に繋げる。
精進料理を通してダーヴィドたちは学びました。
自然界から食材をもらう野草革命、昆虫革命
ダーヴィドたちはさらに旅を続けます。
今度は、京都在住の野草研究科の若杉とも子さんを訪ねました。
彼女は野草を使ったさまざまな料理を作っている人です。
全て無農薬・無肥料の原料を使用して、心と体に優しいものを販売しています。
それら全てが手作業で、丹精込めて作られた商品は、野草茶やお酢、醤油などの調味料のほか、梅干しの黒焼きなどもあります。
「 ほとんどの野草が天ぷらとして活用でき、野草の力で病院知らず 」だと語る若杉さんは、実に朗らかで、お元気そうです。
ダーヴィドたちも一緒に野草を取りに入り、若杉さんの説明を受けながら、さまざまな食材(野草)を手に入れました。
野草の中をかき分けて入っていくダーヴィドとニキ。
一歩一歩、足元を見ながら、歩きます。生い茂った草花はどれも貴重な食材だからです。
このあと一行は、若杉さんと娘さんと一緒にご自宅で野草の天ぷらを食べるのですが、そのときの若杉さんの言葉が印象的です。
「 食べ物は体を変える、すると心が変わる、生き方も変わる、食があなたを作る 」
この映画で一番心に響いた言葉でした。
さて、経験豊富な82歳の若杉さんの次に登場したのは、若さとアイデアでフードロスに挑む男性、「 地球少年 」の篠原祐太さんです。
地球少年とは、昆虫食の魅力を発信し、そのレストランも経営する篠原さんの肩書きです。
彼は昆虫食という分野、なかでもコオロギ食で近年注目を浴びています。
「 虫は嫌われ者ではない、おいしく食べられる 」と言います。
ダーヴィトたちと地球少年が会った場所は河原。近辺には小さい森のような場所も見えます。
まずはここでも皆で食材探し。童心丸出しで飛び跳ねながら、昆虫を探しました。
篠原さんは虫を見つける度に「 これはおいしいんですよ 」などと感想を言います。
一体、何種類の昆虫を食べてきたのでしょう。
さぁ、お昼ご飯にしましょう。
簡易的なテーブルとイスが用意され、メインで出てきた料理は「 コオロギラーメン 」
確かに戦時はイナゴを食べていたと聞いたことがありますが、篠原さんが開発した、コオロギを使った料理はとても斬新でした。
コオロギで出汁を取り、麺の中にもコオロギの成分を入れ、トッピングもコオロギです。
これを食べたダーヴィドたちは、「 おいしい!コオロギだなんて思えない! 」と大絶賛でした。
皆で川の近くで食べていたせいか、感想の声もリアクションも大きいです。
開放的な屋外で食べるという変化球は、コオロギラーメンをおいしく感じさせる見事な演出でした。
もったいない暮らしは楽しい工夫で満ちている
いよいよ、映画も終わりに近付いてきました。
ダーヴィドのキッチンカーを舞台に、「 もったいないパーティー 」が開かれたのです。
そこには、残った食材や消費期限切れの食品を集めて作った、数々のオリジナル料理が並びました。
誰もがウキウキ、ワクワク。踊りながら食べる人もいます。
それをキッチンカーから楽しそうに見守るダーヴィド。
このパーティーに集まった彼らは皆、フードロスを義務としてやっているのではなく、
自分のクリエイティブ、オリジナリティを試すかのように意欲的です。
楽しそうな人々が映し出される画面からは軽快なリズムも聞こえます。
牧歌的に生きよう、自然と調和することでフードロスを防げるよ。
そんな台詞が聞こえてきそうなラストシーンに、この映画の全てが込められている気がしました。
フードロス対策の第一歩は、使いやすいキッチン環境を整えることです。キッチン・台所まわりの設備トラブルは食材の無駄にもつながりかねません。キッチン・台所の修理や点検でお困りの方は「 水道修理のセーフリー 」がおすすめ。
最後に
実は、今回の記事では書ききれなかった食材救出人たちが存在します。
前述の、「 あるものを工夫して食べる 」とは異なる手法、「 再利用 」という形で、貢献する人々です。
ペットボトルを豚の餌にして再利用する企業。
家庭から集めた生ゴミで段ボールコンポストを作り、それを元に野菜を栽培、生ゴミを提供してくれた家庭にその野菜を戻す女性などです。
出演者全員に共通していたのは、「 もったいない、残念だ 」という気持ちが見えないということでした。
むしろ、ここが腕の見せどころとばかりに、どの人も楽しそうでした。
このように、本作はいくつもの観点から、「 食べること 」について考えさせてくれます。
映画の核である食品廃棄という深い社会問題を、ダーヴィドの明るさ、ニキの愛らしさ、そしてこの問題に前向きに取り組む
出演者たちが盛り上げていたことは言うまでもありません。
ユニークな取り組みで立ち向かう人々から、結果的にダーヴィドたちが勇気と喜びを与えられたのです。
捨てられがちな可食部を残さず食べること、消費期限切れの食材を上手に利用すること、
買わずに手に入る野草や昆虫を食べる工夫はどれも、私たちの創造性を刺激しました。
一見難しく思えますが、私たちがすぐにでも実行できることはあるはずです。
まず、買いだめをやめることから始めませんか?
牛乳など、賞味期限の近付いた手前の商品から買いましょう。
楽しみながら、SDGsの12番「 つくる責任、つかう責任 」について考えたいですね。
 執筆者
執筆者文・ライター:栗秋美穂
↓そのほかのドキュメンタリー作品レビューはこちら↓
「 荒野に希望の灯をともす 」の映画情報・あらすじ・レビュー