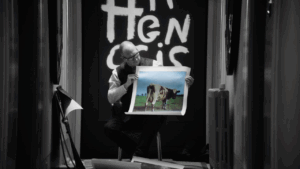オオタヴィン監督の作品は「 いただきます 」の頃から好きだった。
子育てに悩んでいた私は、子どもと短時間でも離れたかったこと、この映画なら子育てのヒントになりそうなことを言い訳に、当時2歳の息子を夫に預け、ママ友と見に行った。
素晴らしかった。口にした全てのものが体を作る。我が子の体はもう自分の体とは分離したが、幼少時の体づくりこそ、大切だと実感した。
手作り食品やオーガニック食材を押し付けることなく自然と「 これが素晴らしいことなんだ、自分も我が子に食べさせてやりたい 」と思わせる作品だった。
子どもの表情に、それはそれは丁寧に追っていた。
あの作品は全ての母に「 母としての活力 」を与えたと思う。
それからも何作かこの監督の作品を見ている。「 夢みる小学校 」も感動的だった。
今思えば、増え続けている現在のフリースクール、オルタナティブスクールの原点がここにあると思う。
筆者は個人的な理由で3年前から28校のフリースクールを取材した。
さらにサードプレイスの運営に携わり、ホームスクールを経験したこともある。
だからこそ、どのスクールや学校も、運営者は少なからずこの作品に影響を受けているように思えた。
そういう意味で「 夢みる小学校 」が多くの子どもに居場所を与えるきっかけになった功績は大きい。
「 視聴後に人が自ら行動する 」というドキュメンタリーの役目を十分に果たしたと言えるだろう。
エンターテイメント☆ドキュメンタリーとは何か

そして今回の「 夢みる校長先生 」である。
なるほど「 エンターテイメント☆ドキュメンタリー 」という新しいジャンルを銘打っただけのことはある。
ドキュメンタリー性よりエンタメ性が強くなり、「 魅せる 」ことに注力しているように感じた。
また、エンターテイメントなのか、ドキュメンタリーなのか分からなかったが、私はそれでいいと思う。
「 夢みる 」のだから、おもしろくなければ意味がない。
次々と登場する校長先生たちの取り組みは、通知表なし、テストなし、宿題なし。
そして探究活動を極めるーー。ある意味「 破天荒 」である。
こうした取り組みを保護者たちに丁寧に説明し、理解を得て展開していった校長先生たちを尊敬する。
何よりご本人たちが「 やりたくてやっている 」ところがすごい。
評判になりたいからではないのだ。
しかし、登場する校長先生たちの取り組みはベン図のように重なる部分が多い。
欲を言えば、もう少し先生方の人数を絞り、保護者と生徒の声も拾いながら、オムニバス形式にした方が、この作品は光ったと思う。
何せ、登場人物は一級の素材。調理次第でもっと色んな側面が出てきたはずだ。
初期に比べて「 伝えよう 」という気持ちより「 紹介する 」という手法にシフトしたのかもしれない。
展開が「 校長先生たちの自己紹介 」を羅列しているように思えたのは私だけだろうか。
夢のあとを描かずしてドキュメンタリーと言えるだろうか
オオタヴィン監督の作品はもはやブランドになった。
自主上映であるのに、行列は当たり前。見られない上映館が続出した。
筆者も3回目の上映会申込でやっと鑑賞できた。
熱心なリピーターもいた。このシリーズなら間違いないと思っている人もたくさんいるだろう。
だが、映画も監督もスタッフも、長くやればいい意味でも悪い意味でも変化していく。
今回の作品に、初期のような「 迷える母たち 」を動かすパワーはなかったように思う。
エンターテイメントなら「 夢みる 」で成立するが、ドキュメンタリーとしては、後追い取材も大切である。
公立の学校の場合、校長先生が学校を去れば、次の校長の采配で新しい学校に生まれ変わってしまうという、大切な事実を描かなかったことが残念でならない。
「 あの校長先生のいる学校に行けば立ち直れるかもしれない 」ーー。
切実な思いでその校区に引っ越したとしても、校長が変わればそれまでのやり方も変わる。
もし登場する校長先生をもっと絞り込んで丁寧に追っていけば、その負の側面にも迫ることができただろう。
また、教育という観点だけでなく教育移住というテーマも浮かび上がってきたかもしれない。
他にも、もっと迫ってほしかった先生がいる。
ある校長は熱心に勉強してエビデンスを集め、コロナ禍に学校行事を敢行。結果、感染者ゼロにした。
彼は、子どもたちに「 思い出 」という宝物をプレゼントしたのだ。
また、「 夢みる弁護士 」の活動にもう少しフォーカスすれば、「 校則をなくす 」ことが最適解ではなく、「 変える 」という選択肢もあることを示せたかもしれない。
筆者が一番気になったのは、校長先生の取り組みよりも生徒の気持ちである。
在籍中の保護者は、校則も通知表もテストもなくなったことを理解した。
しかし肝心の「 在校生たち 」がそれに満足したかどうか、ほとんど触れられていない。
作品の終盤に登場し、肯定的な意見を述べた卒業生一人のコメントだけでは、この学校改革の良し悪しを判断することは難しい。
前述したように、独自取材した学校が28校あるので、作品に登場したいくつかの学校を知っていた。
生徒の中には、ある程度ルールがあった方が動きやすい子もいるはずだ。
自由すぎて学校が落ち着かない。授業中の出入りも自由。
勉強の環境が整わず、家でオンライン塾を利用して高校受験に挑んだ子もいた。
校則がなくなったことでスマホによるいじめに苦しんだ親子も実在する。
通知表をなくしたら、高校進学時の内申点はどうなるのだろう。
「 エンターテイメント☆ドキュメンタリー 」だから、そのような現実的なことを描かないのかもしれない。
しかし、視聴者(保護者)に「 いい面 」しか伝えられていないという点で、私はこの作品を「 ドキュメンタリー 」として捉えることは難しかった。
物事の表と裏を多面的に照らし、真実を浮き彫りにするのがドキュメンタリーだからである。
小学校や中学校でこのような「 子どもファーストな学校 」を卒業しても、次のステージはいわゆる「 普通 」の、校則も制服もある学校がほとんどなのである。
環境の変化に戸惑い、通信に編入した子も知っている。
楽しいだけではない「 戦場 」である学校
何度もしつこいと思われるかもしれないが、登場人物である先生たちの素晴らしい取り組みを紹介したら、その裏にある現実を映し出してほしかった。
説得力が違うからだ。
そして、それがたとえ厳しい現実であっても、この力ある監督ならエンターテイメント☆ドキュメンタリーにできたはずだと私は思う。
どうして監督は現実を知らせなかったのであろうか。夢だけ見せて、それで作品は終わりなのだろうか。
もしかしたら、今では倍率も1.1倍となった教員採用試験に配慮して、教員志望学生に「 夢を見せたかった 」のだろうか。
努力をしている先生は知っている。一方で若い教員の質が下がっているのも否めない。
その現役の若い教員や、教員志望者がこの作品を見て「 自分も校長になって理想の学校を作る 」と思ってくれたなら、この作品は意味を持つだろう。
厳しいことを書いたが、ヒットメーカーである監督にしても作家にしても、世に出す全ての作品が一流だとは限らない。
「 人間 」という生き物が作るものに「 絶対 」はないのだと自覚しながら、毎回、新たな気持ちで考察に挑んでいるからこそ、それを実感して伝えた。
かく言う筆者も、デビューしたばかりの頃に書いた考察を読み返すと、「 感動 」だけが伝わってくる「 感想文 」だ。
考察に至っていないと苦笑せざるを得ない。
校長先生たちが見た「 夢 」を、長く長く続く現実にするためには、その裏側で起こる課題から目を逸らしてはならない。
この作品を見て、一瞬「 夢みるおばちゃん 」になった筆者は、ドキュメンタリー考察ライターとしてあえて否定的な意見も述べた。
そしてこの作品を見たことで「 小学校~それは小さな社会~ 」が「 現実を忠実に撮影した 」という点で「 ドキュメンタリーとして評価された理由 」が理解できた。
次回作「 ハッピー☆エンド 」は2025年4月18日からアップリンク吉祥寺で公開される。
エンターテイメント☆ドキュメンタリーからハートフルドキュメンタリ―になるという。
どんどん登場人物の年齢が上がっているオオタヴィン作品。
今度は高齢者が中心なので、耳の聞こえづらい人、目の見えづらい人が訪れるかも知れない。
そうした人たちへの配慮をしてほしいと願う。それこそが「 ハートフルドキュメンタリー 」なのだから。
 執筆者
執筆者文・ライター:栗秋美穂
「 小学校~それは小さな社会~ 」の映画情報・あらすじ・レビュー