2025年1月28日、都内某所で上映されたドキュメンタリー映画『 花束 』、上映後、アフタートークショーが行われました。
監督のサヘル・ローズさん、俳優の佐藤浩市さん、キャストのブローハン聡さんのお話をお届けします。
※ 一語一句は書き取れませんでしたので、筆者の要約も含まれております。

ブローハン聡さん:1992年生まれ。11歳から19歳までの8年間、東京都の児童養護施設で過ごす。現在は講演活動、児童養護施設3人組ユニットのYouTubeチャンネル『THREE FLAGS-希望の狼煙』こども家庭庁審議会臨時委員、一般社団法人「コンパスナビ」代表理事として活躍。著書「虐待の子だった僕―実父養父と母の消えない記憶」ここに書影提供予定
佐藤浩市さん:1960年うまれ、東京都出身1980年、NHK「 続・続月の景色 」に主演し俳優デビュー。その後、俳優として数々の賞を受賞。2019年より週末里親のフレンドパークを経験、児童養護施設の子どもや社会的擁護の若者と交流を深める。
サヘル・ローズさん:イラン出身。孤児院で過ごし、7歳で養子縁組、8歳で養母と共に日本へ。舞台「悲しき娼婦」で主演を務めた。映画「冷たい床」でも主演を務め、様々な映画祭にて賞を受賞。近年では演出、監督とマルチに活躍し、表現者としての幅を広げている。2024年新著「これから大人になるアナタに伝えたい10のこと」サヘル・ローズ著(童心社) 初の絵本「 Dear 」サヘル・ローズ著(イマジネイション・プラス)
ーーサヘル・ローズ監督(以下監督)
実は私、天秤座なんですけど、今日は最下位だったんです。それなのに、今日は(場内)満席なんです。そして何より、こうして(佐藤)浩市さんと一緒に登壇できるなんて!素敵な一日、改めてよろしくお願いいたします。
ーー佐藤浩市さん(以下、浩市さん)
どうも、こんにちは。ありがとうございます。本当にいろいろ考えたい、考えさせてくれる作品です。
ーーブローハン聡さん(以下、聡さん)
撮影していた5年前、当時は児童養護施設について発信する、自分の生い立ちについて話すと言うことはほとんどありませんでした。ただ、家族のこと、血のつながりで困っていました。経済的にも(少し言葉を濁しながら)ひっ迫していた状況で、とてもつらい26歳を過ごしていました。
その時、佐東亜耶さんやその他の人、児童養護施設をサポートする団体と出会い、当事者として発信する若者たちを見て、ご自身もそこから何か発信してみようと思われたそうです。(プロフィール参照)
ーー聡さん
当時の僕のイメージは、さきほどご覧いただいた通り(本編のこと)です。皆さん、僕が身構えて話したり、ちょっとかわいそうなど、いろんなイメージを持って来られたと思います。僕自身も当時は児童養護施設について話すと言う事自体、抵抗感がありました。でもその理由は、こんなにたくさんの大人たちが関心を持ってくれていることで変わりました。
聡さんは、自分を含むたくさんの若者が話せば話すほど、悲しい出来事として終わるのではなく、周囲が解決策を考えてくれる機会がたくさんあったと言いました。
ーー聡さん
そこから5年、走ってきました。そしていまではさまざまな表現方法で発信しています。その中で僕が最も大切にしているのは、作品一つどれをとっても言葉ひとつでも、変わる瞬間を誰もが持っている、それを信念に持って動いてきたということです。
ーー浩市さん
いろんなご縁の中でこの映画に参加することになりました。そして感じるのは、子どもたちみんな地球の上で生きている。世界ですね。
そうすると、やはりポリティカルスタイルも違えば、メイン宗教も違う。明らかに習慣も違っていて、本当に全然違う国々、世界がある。いろんな国があるんです。だけど、共通していることは、不幸になるのは子どもたちということ。
弱者に対するいろんな意味での社会的な抑圧、そういうことが子どもたちに向けられてしまう。これを何とかしなきゃいけない。
決めつけてかかる人間がいるから子どもがかわいそうなんです。『 ~はあれだからああなんだ 』とか決めつける人間、大人たちが子どもたちを不幸にするということ、それを僕らがひとつずつ無くしていき、偏見なく子どもたちに向き合ってください。うつむいてばかりいるような、そんな子たちばかりではない 。
ーー監督
浩市さんは本当に言葉に力がある人で、私は浩市さんを尊敬しています。私は言葉に詰まりますね(実際、監督が涙ぐみながら話す)私にも血のつながりは誰もいないです。
養母と二人で生きていく中で生き方が分からなかったり、自分の生い立ちを誰と共有していいか分からなかったり、言葉の壁もありました(このあたりは前述の著書『 これから大人になるアナタに伝えたい10のこと』(童心社)の前半に詳細に書かれています)でもこの映画を作りたかったのは、ただただ自分の経験を無駄にしたくない。
誰かの過去の出来事が誰かにとっては必要なエネルギーに変わる瞬間がある。この映画を通して、特別に何かを押し付けたいわけでは全くないです。
だけど、こういう問題啓発をしていくことで、まず社会的養護、親と一緒に生活できない人、そしてその裏側を全部含めて一番誰が苦しんでいるか。大人の苦しんでいる姿を見た子どもが一番苦しんでいます。実はこの映画は、大人が救われてほしいという気持ちで 7 年かけて作りました。
最後に佐東亜耶プロデュースの言葉です。
映画で世界を変えることはできないかもしれませんが、皆さんが今日受け取ってくださったこの花束の花粉を、どうか他の方々にもつなげてもらいたいです。
そして映画の宣伝マンになっていただきたいです。この映画は本当に種まきをしながらゆっくり育てていき、見てくださった方がまた伝えてくださることをとても強く望んでいます。
文面だけ見ていると、とても緊迫した会場だったように思えるかもしれません。
しかし、途中で浩市さんが聡さんに「 おい、話しが長いぞ 」とからかう場面もありました。舞台上でこのようなやり取りもできる信頼関係が、長い年月の中で培われてきたのだと筆者は思いました。
レビュー
物語はなんと全編においてモノクロだった。
キャストへの生い立ちインタビューと、その彼らが「 演劇 」という表現を通して、どう自分を解放していったか、その経緯を丁寧に撮影した「 実験映画 」である。
この映画において、キャストが「 インタビューされる 」と言う形で自身を語るというのは非常に大切な意味を持っていたと思う。
彼らはまるで他人事のように自身の生い立ちを話す。話し続ける。それが大切なのだと思った。
複雑な生い立ちを話せば、たいていの人なら途中で話をさえぎり「でもさ…だけど頑張ろうよ」というようなことを言いそうだ。
それは聞かされた相手も、なんて答えていいか分からないからだ。
だからこのキャストたちはおそらく、自身のことを深く「 話し続けた 」ことはないだろう。
独白に近いそれを、監督とスタッフはあまり質問をせず、彼ら一人一人の言葉を待って、丁寧に心情を引き出していた。
その後に、そういう生い立ちを持ったキャストが出てきて芝居をする。
―――窓際に座り、モノクロの場面でも光る月とそれを覆う雲を見たキャストの青年が、電話をしている。相手はガールフレンドだろう。
「 会いに行っていい?」「今から?」「そう今から(笑いながら)声を聞いたら会いたくなったよ 」と。
監督が彼らの話に傾聴し、共感することで、この青年は思いを吐き出すことができ、素直に「 会いたい 」と言える芝居ができたのだと思う。
もしかしたら芝居ではなかったかもしれない。キャストの誰もが演技のプロではないのに、監督がインタビューと演劇を掛け合わせた
演出をしたおかげで、かれら皆が本物の役者になっていった。
それは終盤に迫れば迫るほど、セリフに命が宿っていったように思う。
ラストシーンで、皆が「 ある言葉 」を叫ぶ。
その言葉に筆者は彼らの「 親への愛 」を強く感じた。
子どもは親を愛してやまない。親もまた、子どもを愛してやまない。それは「真実」であるのに、一定の人たちにとっては「真実」ではない。
真実を取り戻すために、何ができるのだろうと、私がドキュメンタリーにこだわる理由がひとつ増えた日だった。まずは、この「 花束 」を多くの人に届けること。
この後、メイキングドラマの記事や監督独占インタビューが続きます。
どうか一本のドキュメンタリーを、筆者と、そして「 シネマライブラリ 」と共に深堀してください。
 執筆者
執筆者文・ライター:栗秋美穂



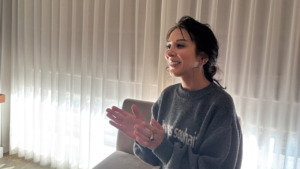




-300x169.png)



