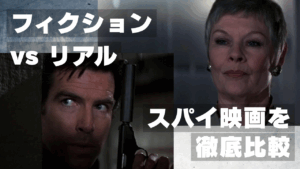映画というジャンルを超え、現代のカルチャーシーンに大きな影響力を持つフランスの映画監督、ジャン=リュック・ゴダール。
多くのシネフィルから熱狂的支持を得ている伝説の巨匠だが、今時のシネコンに映画を見に行くごく一般的な映画ファンは、どれだけ彼の映画を知っているのだろうか?
語られることこそ多いが、見られることは少ないゴダール映画。
しかも決して万人受けするタイプの作品ではなく、かく言う筆者もゴダール映画に長年苦手意識を持ってきた。
なぜ自分はゴダール映画が苦手なのか?
久しぶりに見た2本のゴダール映画をもとに、その謎に迫ってみる。
自意識過剰なゴダール信者にはうんざり

ジャン=リュック・ゴダール(1930〜2022)といえば映画史に名を残す巨匠であり、いわゆる「 シネフィル(映画好き、映画通) 」から神のごとく崇められている映画作家だ。
特に日本では蓮實重彦の影響力が非常に大きいため、蓮實信者がそのままゴダール信者となり、「 ゴダールのよさが理解できないやつは映画というものを理解できていない 」、
裏を返せば「 ゴダールのよさが理解できる自分は映画というものを理解できている 」と言いたいがためにゴダールを祭り上げている輩が少なくない。
そんな自意識過剰なエピゴーネンの存在には、長年うんざりさせられてきた。
かくいう私は、基本的にジャン=リュック・ゴダールが苦手である。
「 勝手にしやがれ 」(1960)にせよ「 気狂いピエロ 」(1965)にせよ、あの映画話法が当時としては斬新だったことは分かるが、その影響下から生まれたアメリカンニューシネマに先に親しんでいた者としては、「 ドラマ 」として、ニューシネマほどの感動は覚えなかった。
つまらないとまでは言わないものの、そこまで絶賛するほどか?という感じで、先述のような熱烈な信者の存在とあいまって、長い間敬遠する意識の方が強かった。
「 はなればなれに 」「 ウイークエンド 」のハシゴ
そんな私が久しぶりにゴダール映画を見た。それも劇場で2本ハシゴだ。
作品は「 はなればなれに 」(1964)と「 ウイークエンド 」(1967)。
大きな理由は、「 ゴダールが苦手な人にこそ受ける 」と前から耳にしていた「 はなればなれに 」を見たかったからだ。
そして「 ウイークエンド 」も彼のフィルモグラフィの中では、自分でも楽しめる作品だろうという予感を前から抱いていた。
苦手だった作品や監督も、年月を経て見直すと印象が変わることがある。
そのような期待を抱きつつ劇場に向かった。
「 さらば、愛の言葉よ 」(2014)を見て以来だから、8年ぶりのゴダールだ。
結果、「 やはり苦手だ 」と思う面も多いが、全体的には大いに楽しむことができたし、色々と考えさせられたので、それについて書いてみたい。
「 人間のための映画 」ではなく「 映画のための映画 」
「 はなればなれに 」は、「 勝手にしやがれ 」とトリュフォーの「 突然炎のごとく 」(1961)を足して2で割ったような内容。
前半はなぜ私がゴダールが苦手なのかがよく分かる作りだが、後半は毛色が変わり、最終的にはなかなか楽しい作品となっていた。
私はなぜゴダール映画が苦手なのか?
第一の理由として、一般的なストーリーテリングや演出・編集から大きく外れた実験的な作りが挙げられる。
実験的であること自体はいいのだが、映画の定型を破壊することが第一の目的と化し、「 人間 」や「 物語 」が二の次になっていることに抵抗を覚える。
つまり、「 映画のための映画 」であり「 人間のための映画 」ではない。
いささか極端な言い方をするなら、「 映画そのもの 」ではなく「 映画というものに対する批評 」や、下手をすれば「 映画作りのための参考書 」のようなものだ。
それを通常の映画として見たら、つまらないのも無理はない。
ゴダール信者の言説の大部分が退屈なのは、その点を曖昧にしたまま、もしくは「 そんなことは最初から分かりきっている大前提だ 」と言わんばかりの不親切さで、ゴダール映画を通常の映画と同列に語るから。
これも極端な例えだが、一般的な小説とカメラの撮影マニュアルを、同じ「 本 」として同列に評価すること自体おかしいのと同じだ。
生きた人間としてのリアリティの欠如
それと大いに関係するのだが、久しぶりに見て、今回やっと言語化されたゴダール映画の苦手ポイント。
それは「 人間の言動にリアリティの欠片もない 」ということだ。
「 はなればなれに 」の前半では、それが炸裂しまくっている。
そこで展開されるのは、ごく普通の人間なら到底しないような行動、会話、思考、他人とのコミュニケーションばかりだ。
主人公3人の言動は、ほぼその異質さだけで構成されている。私にとってはまるでエイリアンだ。
具体的な例を述べ出すとキリがないので、知りたい方は実物をご覧になるといいだろう。
もちろん映画の登場人物が平凡な現実そのままの言動をしないのは当然のことだが、ゴダール映画の場合、それがあまりに極端なのだ。
会話の内容やリズム、ちょっとした動作に至るまで、全てが日常生活の中で見る人間と違いすぎる。
あんな連中が同じ電車内にいたら、「 危ない人たちだ 」と別の車両に移るレベルだ。
実はこれまで、そういう異質さは、日本とフランスの文化習俗の違いとして捉えていた面がある。
確かにそれもあるだろう。
あるだろうが、それだけで片付けられる話ではないことに、ようやく気が付いた。
なぜなら、そのような異質さは、ヌーヴェルバーグとその流れを汲む一派(レオス・カラックスなど)に顕著な特徴で、他のフランス映画ではそこまで目立たないからだ。
日本人よりは主張も反応も強めだが、エイリアンというほど極端ではない。
考えてみれば、昔実際に行ったフランスもそんな感じだった。
ヌーベルヴァーグは基本的に演出や編集、脚本軽視などの技術面で特徴付けられる流派のはずだが、こういう「 極端に戯画化された(=非現実的な)人間の行動様式 」というのも、一つの伝統として受け継がれてしまったのだろう。
長々と書いてきたが、簡潔に言うとこうなる。
「 ゴダール映画の登場人物には生きた人間としてのリアリティが感じられない 」
ゴダール映画は漫画のような非リアリズム作品として見るべし
では後半はなぜ楽しめたかというと、前半よりもストーリー性が出てくるのに加え、ずっと見ていくうちに、その戯画化された登場人物にだんだんと慣れて、愛着が感じられるようになってくるからだ。
これは現実的なリアリティが希薄な漫画のキャラクターに感情移入する過程によく似ている。
問題は、漫画ならメディアとしての特性上こちらも即座に受容のチャンネルが切り替わるのに対し、ゴダール映画は特にファンタジーというわけでもない実写映画なので、登場人物を漫画のキャラと同じように見る切り替えが難しいという点だ。
そのため見方を間違えて、置いてけぼりを食う。
しかし「 ゴダール映画は漫画と同じような受容の仕方でよいのだ 」と割り切ってしまえば、人物描写で気になる点はかなり解消される。
いちいちナレーションが入って物語や人物の心理をメタ的に解説するのも、最近の漫画によくある手法ではないか。
そのように視点を変えて臨むと、これがなかなか楽しい。
何よりも「 はなればなれに 」はコメディだ。
肝心の強盗シーンのどうしようもない行き当たりばったりさ、それに対する登場人物のリアクション、人を食ったような演出。
これは大いに笑える。
そう、これは小難しいことを考えずに笑って楽しめる映画なのだ。
もちろんそこで駆使されている映画技法は、功罪両面において映画史についてあれこれと考えさせてくれる。
だがひとまずは、いくつかのジャンルがごちゃ混ぜになったコメディとして見ればいい。
「 ゴダールが苦手な人ほど楽しめる 」というのは必ずしも嘘ではない。