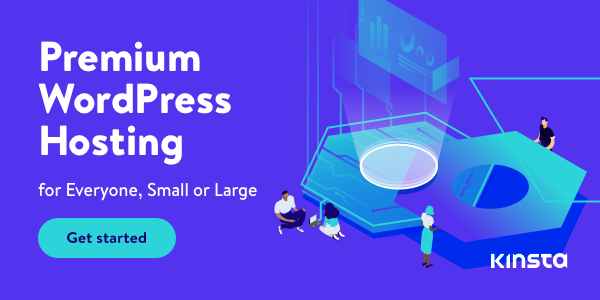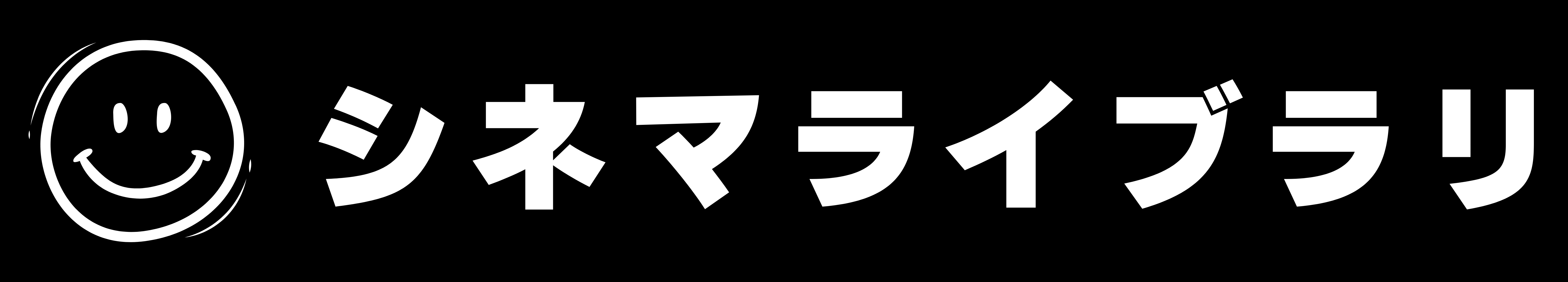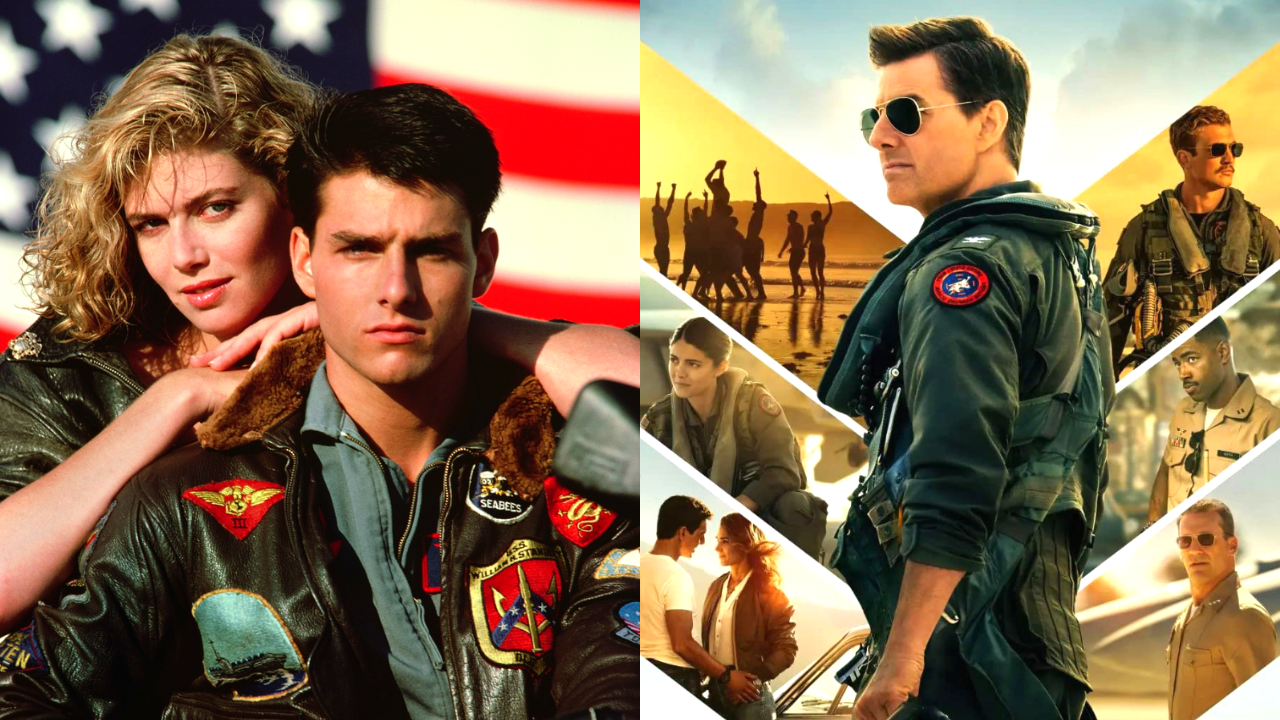「 旅立つ息子へ 」ネタバレなし考察レビュー

映画ライフ楽しんでますか?
今回は、ペンネーム(@ジョナ)さんからの投稿レビューです。
お涙チョーダイ映画が苦手です。
泣くために映画を見るのではないからです。
映画を見て涙を流したことも、数えるくらいしかありません(小説も同様)
しかしながら、今作はハンカチならぬマスクの替えが必要だったなと後悔しました。
子を持つ親なら尚更でしょうね。
本記事では、今作の魅力と自閉症スペクトラム(以下ASD)の主人公を描いた他の作品について書いてみます。
画像の引用元:IMDb公式サイトより
(アイキャッチ画像含む)
旅立つ息子へ

公開日
2021年3月26日
上映時間
94分
原題
Here We Are
キャスト
- ニール・ベルグマン(監督)
- シャイ・アヴィグィ
- ノアム・インベル
- スマダル・ヴォルフマン
予告編
公式サイト
作品評価
[rate title=”5つ星”]
[value 4]映像[/value]
[value 5]脚本[/value]
[value 4]キャスト[/value]
[value 3]音楽(BGM)[/value]
[value 3]リピート度[/value]
[value 1]グロ度[/value]
[value 3 end]総合評価[/value]
[/rate]
感想レビュー

好きだった点
元有名デザイナーである父親(アハロン)が、自閉症(ASD)の息子(ウリ)を見守る眼差しや、些細な言動の数々がこれまで多くの苦労と愛情を重ねてきたのだと自然に分かる点。
壁に貼られた様々な形のスイッチのイラスト、一緒に歩くときにステップを合わせる仕草。
ウリのお気に入り(チャップリンの映画、金魚の一家、星型のパスタ……)を完璧に把握しているアハロンの子育てへの並ならぬ情熱が、ウリの安心しきった飛び切りの笑顔に反映されていました。
特に好きなシーンは、旅先の遊園地で父子が飛び跳ねながらダンスするシーンです。
男手ひとつで子どもを育てる(ASDの青年が主人公の)物語といえば「 アイ・アム・サム(2001年)」が代表的です。
サムは大のビートルズ好きでしたが、ウリは大のチャップリン好き。
主人公の好きなものが、自分の好きなものと同じだというのはとても嬉しいですね。
嫌いだった点
本編とは離れますが、お涙チョーダイ映画として宣伝されている点。
「 世界中が大粒の涙 」「 感動!」と謳われてしまうと、見る前から構えてしまい、素直に鑑賞できなくなってしまうので、どうにかならないかなあ、と思います。
世界中が見る訳でもなければ、感じ方も人それぞれですから。
まあ、ずっと涙流しながら見てましたけどね(笑)
「 泣ける 」というのはネタバレに等しいので、せめて「 涙 」という単語を使わずに宣伝できないかなあと思うのです。
見どころ
真実味のこもったストーリーに注目です。
脚本家の父と弟がモデルとなっていることも、実際の家庭を取材して製作したことも、今作のリアルな描写に関係していることでしょう。
父と息子の演技が格別に良いです。
アハロン演じるシャイ・エヴィヴィの孤独と慈しみをたたえた瞳と演技は、イスラエル・アカデミー賞主演男優賞を受賞したベテラン俳優ならでのものでした。
演技とは思えないほどASDの青年を見事に演じた新人ノアム・インベル。
「 ギルバート・グレイプ(1993年)」で知的障がい者を演じた、レオナルド・ディカプリオの再来とも言われています。
表情、姿勢、手の動き、声のトーン、全てが演技とは思えないほどです。
ちなみに、今作の撮影後からノアムはASDの人たちを支援する施設にボランティアで通っているそうです。
考察レビュー

今作の他に、自閉症を持つ人と家族を描いた作品はあるのでしょうか。
先述した作品の他には「 シンプル・シモン(2010年)」が記憶に新しいです。
他に、発達障がいの子と母を描いた作品では「 MOMMY マミー(2014年)」も色々と考えさせられる名作でした。
今作の予告編で知った、現在(2021年4月)公開中の「 僕が跳びはねる理由 」が、自閉症者を理解するための架け橋となりそうなので、見てみたいと思います。
国によって障がいの考え方や福祉制度の違いはありますが、作品で描かれている限り、まだまだ社会的な関心やサービスは足りていないように感じます。
まずは、知ることから。
今回、初めてイスラエル映画を見ました。
誤解を恐れずにいえば、とても日本的だと感じました。何処となく文化的な類似点があるのかも知れません。
あるいは、監督が、小津安二郎、黒澤明、北野武、是枝裕和といった日本人監督をリスペクトしているというのも関係しているのかも知れません。
まとめ

お涙チョーダイ映画が苦手だと書きましたが、苦手なのは宣伝にあったようです。
泣くために映画を鑑賞するのではないですが、鑑賞してその結果として涙を流すことは、とても気持ちの良いことだと今作に教わりました。
涙を流すのは、感情が動いたから。
これからも涙を流すほどの感動作に、出会えますように。